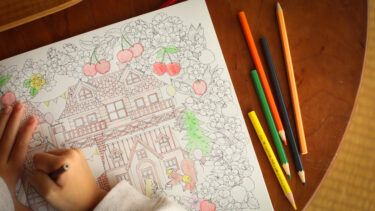InstagramのDMでいただいたご質問。
「高校2年生と小学2年生の子ども。高校生は配膳の手伝いをするが小学生は手伝わない。
このことに高校生は不満があって食事中の空気がギスギスしている。こんなときどうしますか?」
わが家は小1と年長の姉妹なので、子どもの歳の差のある場合、そして高校生ぐらいの年齢の子どもとの接し方が未知の世界。
なので的確なアドバイス的は差し出がましくてできないのですが、せっかくわたしに質問をくださったので一生懸命答えたい!と思って回答しました。

まず最初に、わたしがこの状況だったら何をいちばんの目的にしたいか、優先順位を考えるかなと思います。
お手伝いの習慣を定着させることなのか。
そうだとすれば、高校生のお姉ちゃんへの対応を考えるべきか、下の妹さんに手伝いに参加してもらえるよう工夫すべきか。
でも、文章をお読みするかぎり、ご質問いただいた方は「楽しく食事をしたい」と思ってらっしゃるのかなぁと勝手に感じました。
そして、わたしだったら、お手伝いのことは一旦置いておいて、自分が全部配膳しても良いから、とにかくみんな笑顔で席に着いて食べるということを優先すると思います。

「食事=楽しい」という共通認識が無意識下でできていれば、理想論になってしまうかもしれませんが、小学生のお子さんが自然な流れで食に興味を持ち、お箸を並べてくれる日が出てくるとか、配膳じゃなくても料理そのものに関心を持ち始めるとか。
食事は楽しいものだ!という雰囲気にしていて悪いことは起きないと思うのです。

そしてもう一つ思ったのは、そもそも「お手伝い」という概念について見直してみるということ。
例えば、わが家ではお手伝いとして定義していることはありません。それぞれ「自分の身の回りのことは自分でやろう」ということ、それがすなわちお手伝いになっています。
わたしが在宅ワークなのでほとんどの家事を大人がやってしまっているからというのもあると思います。共働きでフルタイムだとこうはいかないかもしれないので、あくまで参考程度ですが。
食事の準備も各自。子供用のカトラリー類は元からちゃぶ台にセットしてあるので、一人分ずつトレーに乗せた食器を運んだり、食べたら台所まで下げてきたりは自分の分だけ。
洗濯物を運ぶのも自分の分だけ。
つまり、自分の分だけの領域にしておくと、できていることとできていないことが目に見えてわかりやすい。
たとえ姉か妹どちらかができていなくても、不利益を被る(親から注意される、準備できていないことで困るなど)は当の本人だけ。
そうすることで姉妹の不公平感はあまり生じていないのでは、と感じています。
とはいえ、布団を敷いたりする作業は個人ずつの線引きがないので、手伝ってくれている長女が「いつも次女は遊んでばっかりやんー」と膨れっ面をしていることもあります。
そういう時は、「ありがとう。手伝ってくれたおかげで今日はラクに布団敷けたわ〜。」とか「腕が痛かったからめっちゃ助かった!」などと具体的なお礼を伝えることで、「報酬」の代わりにしている(なっていないかもしれませんが)つもりです。

このように回答させていただくと、嬉しいご報告が!
ご質問くださった方が早速台所の配置替えをして、お子さんがそれぞれ自分の分を配膳しやすいようにレイアウトを変えられたとのこと。
ビフォーアフターのお写真まで送ってくださいました。
子育て歴はまだまだ浅いわたしなので、こんな回答で大丈夫?と心配もあったのですが、こちらまで嬉しくなるお返事をいただきました。
そしてわたし自身、子どものお手伝いや姉妹間の関係性などについて改めて考えるきっかけにもなりました。