最近、自分で自分に疲れるということはありませんか?
わたしはよくあるのですが、なぜなのか?そのヒントとなる文章と出会いました。
総合雑誌「世界」2025年7月号にあった記述です。
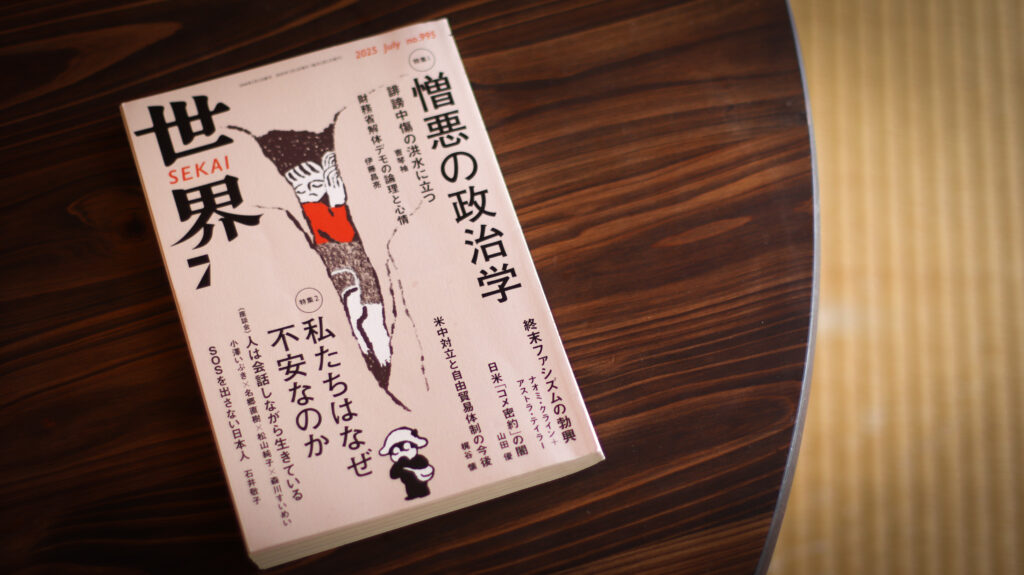
『“自分疲れ”に関しては、自分というものを固定的に考えないほうがいいのではないかと思う。曖昧で、ままならない自分というものを、はっきりした、コントロール可能なものにしようと、人はつねに努力している。具体的には、昨日と今日の自分は同じであろうとしている。矛盾しないようにしている。一貫性があるようにしている。「自分はこういう人間だ」と、自分でも思えるように、他人にも思ってもらえるようにしている。』
『自分を固定しようとすれば、疲れるばかりで、生き生きとはしていられない。自分というのは、もっとグラデーションがあるものだと思う。雲がかたちを変えるように、日々ちがっているものだ。同じ自分ではあるが、同じ自分ではない。』
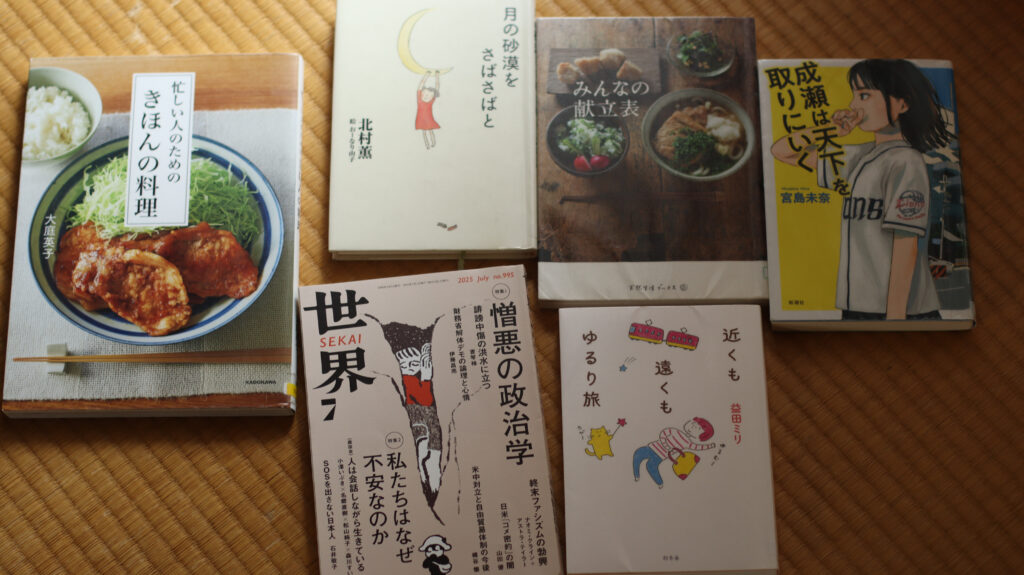
自分はこうであると定義付け、カテゴリ分けをするとそこに縛られて身動きがしづらくなる感覚。
ブログなどで発信をしていると、よくこのジレンマに陥ることがあります。
例えば、「ミニマリスト」という定義なんかが分かりやすいかと思いますが、「自分は〇〇である」と定義付けすると、他人にはどんな人なのか、何を大切にしている人なのかも伝わりやすく、自分でもその定義に沿った行動をすれば良いので選択肢を減らすことができてラクな一面もあります。
ただ同時に、自分で自分を縛っているという事態も引き起こしているのでは。そしてそれも一種の生きづらさに繋がっているのではないでしょうか。
わたしは以前、「部分的ミニマリストを目指して」というタイトルで「服は年間20着で過ごす」というYouTube動画を更新しました。今もその状態は変わっていないのですが、この「20着」を毎回の動画で自分の定義として打ち出していたとしたら。そしてそんな時に、とても気にいる服に出会えたとしたら。
買い足すと21着になります。手持ちの服で手放せる服はない。どうしよう、買うか買わないか。
ここで悩んでいる理由は、発信内容との齟齬が生まれるからなのです。
これまで全面に打ち出してきた発信内容を変えてまで買う価値のある服かどうか。
じゃあ次に服の発信をするときは買い足したことを伝えるべきか、理由も最もなものを考えないと…という思考になる。おそらくわたしが堅く考えすぎだからだと思うのですが、ここまでくると理由というより弁明というニュアンスに近いかもしれません。
これは他人軸とはまた違って、自分が発信した内容と違うことをしようとしている自分に対しての戸惑いや迷い。自分で自分を縛ろうとしていることへの葛藤。
ここでは「本当にその服が自分に必要かどうか」という本質的に考えるべきことが置き去りにされています。
自分を型にはめて定義して発信することで本来悩まなくていいことで悩む、生きづらくなるとまではいかなくても、なんとなくの息苦しさを感じることになるのでは。
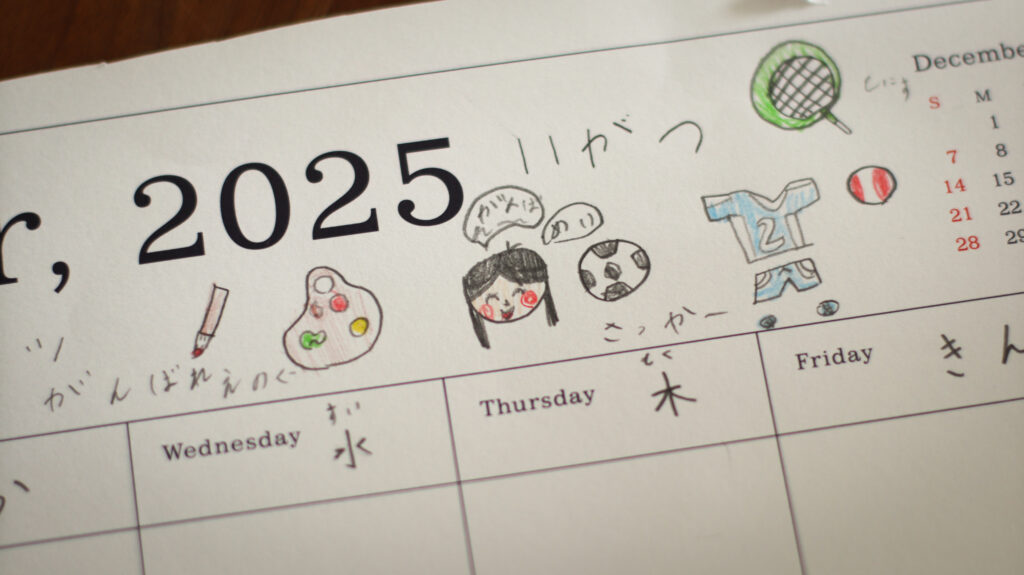
ただ、自分の大切にしていることや定義みたいなものを他人に伝えておくことが功を奏する場面があることも事実。
例えば、わたしはオートファジー生活をしていて夕食は食べないということを家族や仲の良い友達が知ってくれています。
何か美味しいものをお土産にいただいたりすると、夫は昼にワインと一緒に食べようと提案してくれたりします。
ダイエット中!と宣言しておくと、甘いもの以外のおいしいもの情報をシェアしてもらえたり。
習慣や苦手なことを公言しておくことで、そのような誘いを受けることも少なくなり、断り方を考える必要もなくなる=脳を省エネに使える。
でも別の視点から考えると、人生経験としての幅を自分から狭めていることにもなるんじゃないかなぁと思ったり。
あの人はこの時間は食べないからこのイベントには誘わないでおこうとか、これまでもしかしたら気付かないうちに逃してきたことがあるかもしれません。
だから、今日の自分と明日の自分は違うということを前提にして、あまり自分を型にはめすぎない、はめた方がラクに感じてもそれは自分の中だけに留めておいて、あまり他人に明示しないでおこうか。
発信していると、その発信経由でお仕事の依頼をいただくことが多いので、自分を定義付けしないのはなかなか難しいけれど。
何か一本軸が通っている人というイメージを持ってもらった方が好感を持たれると思うけれど。
仕事や今やっていることの肩書きは誰からも分かりやすく明示しておくとして、自分のポリシーのような内的な部分は他言しない方が良い場面があるのかも。

必要に応じて、あえて型にはめてみる。でもそれゆえに窮屈さを感じるものは型から外してみる。
軸がブレブレになるところにその人の人間性が現れるような気もするので、流動的にその時その時の最適解を見つけていきたいと考えています。


