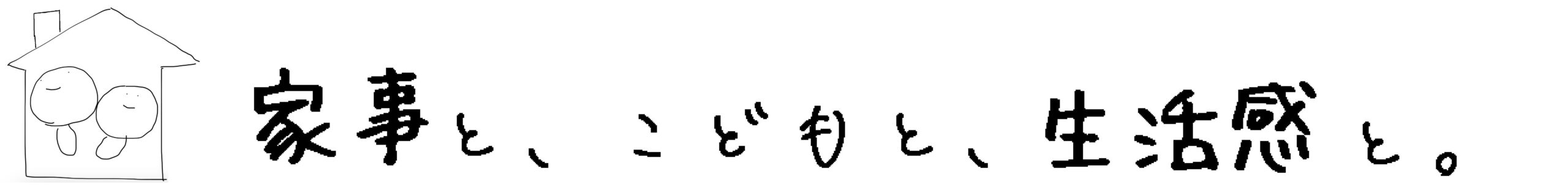食べ物がタイトルに出てきたり、料理がテーマになっている本が好きでよく読むのですが、この『BUTTER』という小説は、これまでのそれとは一線を画したものでした。

多くの食べ物小説(と略します)は、文章を読むとおいしそうな食べ物が頭の中でイメージされ、おいしそう、食べたい、自分も作ってみたいなど、ポジティブな気持ちになることがほとんど。
でも、『BUTTER』で描かれる食べ物の表現は、言葉を選ばずに言うと、グロテスク。
食べる行為とは、生々しい動物的なものであるということをまざまざと思い知らされる、そんな印象を受けました。
頭の中に食べ物のイメージが浮かぶところは変わらないのですが、なんというかそれを口に運んでいる人間味まで食しているところを思い浮かべてしまう、一種の不気味さを持ち合わせている小説。
ストーリーとしては、実際にあった事件(交際相手3人の男性の殺害容疑で逮捕された女性の話)を元にしたフィクション。その被告人を取材する女性記者を主人公に、様々な人間が獄中にいる被告人から影響を受けて振り回されていくーという内容。
読み進めていくうちに、ひとつのことに気が付きました。というほど大袈裟なことではないかもしれないけど。
被告人の女性に振り回された男性は、結果として死に至っています。途中で取材側の女性記者の父親のエピソードもはさまるのですが、彼も離婚して妻と娘が出て行ったあとに生活が荒んでいき孤独死したという結末。
一方で、被告人の欲望に真っ直ぐな言動に振り回され、半ば洗脳されているのでは?というところまで進んでしまうぐらい被告人と関わってきた、関わっている女性たち。危ういところまでいくのですが、彼女たちはそれを踏み台にして、むしろ強くなって生きていく姿が最後まで読むとわかります。
男性、女性、と分けて話したいわけではないのですが、この小説の背後にはケア労働問題が描かれているように思いました。
そう思ったのは、別の本と繋がったからで。
最近読んだ本の中で『アダム・スミスの夕食を作ったのは誰か?これからの経済と女性の話』からの引用がされている箇所がありました。
その引用から、「経済学でケア労働は無視されている」との解釈を読んだのです。
アダム・スミスによると、人間は利己的な欲望をもとに動いているからこそ、経済は日々回っている。
肉屋は金を得るために肉を売り、客はステーキを食すために肉を買う。
でもここで、客がステーキを食べるためには、誰かが肉を焼かなくてはいけない。
ここでは、肉を焼くこと=ケアという観念。
欲望からではなく倫理的な義務によってケア(ステーキを焼く)をする人が必要で、経済が日々回っているのは、誰かが対価なしにケアを担っているからである。
「BUTTER」を読むより先に、こちらの本を読んでいたことで、「BUTTER」という小説の背景には、ケア労働問題が潜んでいるのではないか、と感じたわけです。
被告人に殺害されたとされる3人の男性は、経済的には恵まれた裕福な層に属する人たち。
それなのに、被告人によって提供されていた食事など身の回りのケアをある時から失ったことにより、自殺や自然死とも捉えられかねない死に方をしてしまう。
セルフケアができない男性は被告人に翻弄された結果死に至り(自殺か他殺かはあるとしても)、セルフケアができる女性は、翻弄されたことを踏み台にして、被告人と出会う以前よりもたくましく生きていく。
これはあくまで小説内での仕立てなので、決して男性=セルフケアができない、女性はできるみたいなことではありません。その逆もあると思います。
わたしの夫は、わたしよりも生きていくための生活基礎力みたいなのが高いタイプ。料理洗濯掃除は一通りできるので、わたしが例えば入院したりしてもたぶん大丈夫。

とはいえ、一方で実家の両親や義父母の様子を見ていると、妻側がもし先立った場合、父や義父の生活(ケアの部分)はどうなってしまうのだろうと不安になる。そんなケースも多々あるのではないでしょうか。
「BUTTER」は、食べ物や料理の描写が、タイトル通りバターのように濃厚で、読めば読むほど被告人の女のこともわからなくなってくる、人間味の濃厚さも味わえる小説。
そしてその背景には、ケア労働問題が大きなテーマとしても描かれているように感じました。