「ていねいな暮らし」と聞くと、どんなことを想像しますか?
コーヒーを豆から挽いて飲むこと、季節の手仕事を楽しむこと、出汁をきちんととること?
SNSでも「ていねいな暮らし」というハッシュタグを度々見かけますが、これはしばしば揶揄や批判の対象になることがあります。
なぜ、一見良いイメージに感じられる「ていねいな暮らし」が揶揄されるのか?
最近、そのヒントになるような本を読みました。
「ていねいな暮らしの系譜-花森安治とあこがれの社会史-」(著者:佐藤八寿子)
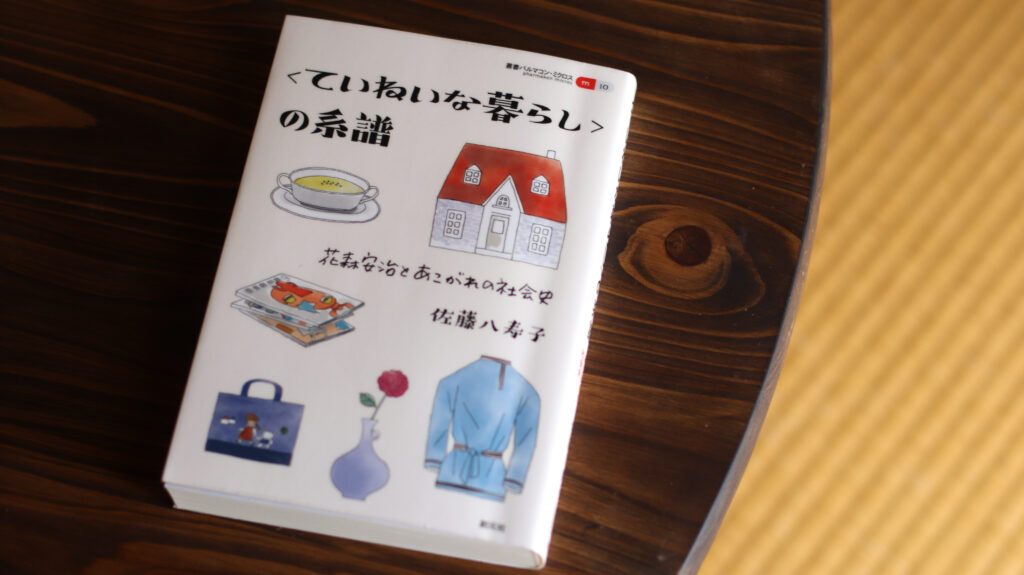
生活雑誌『暮しの手帖』と、その創刊者である花森安治の生き方から、「ていねいな暮らし」が日本でどのように息づいてきたかを紐解く本。
一見、「ていねいな暮らし」を礼賛する内容かと思いきや、淡々と歴史を辿り、事実と照らし合わせたうえで、本の最後には、この言葉が揶揄される理由についても触れられています。
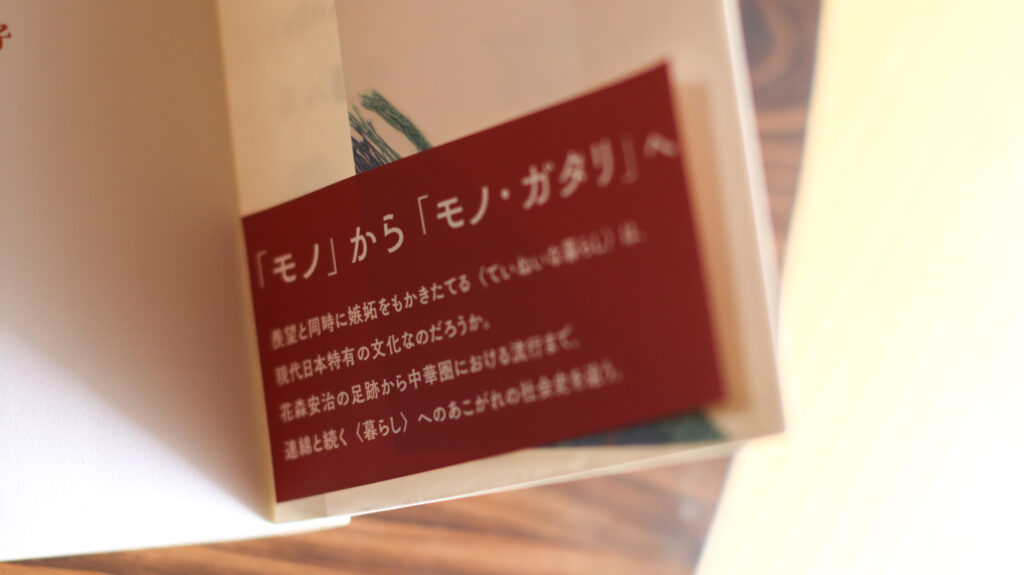
この本を読んで、「ていねいな暮らし」が揶揄される背景には、主に3つの理由があると読み取りました。
簡潔に言うと、目的の不在・自己完結性・優劣を産む構図、の3つです。
「ていねいな暮らし」と似た意味合いの言葉として「凡事徹底」が挙げられていました。この言葉との対比により、より「ていねいな暮らし」が揶揄される理由が分かりやすくなったので、この点も踏まえてお話したいと思います。
ちなみに、「凡事徹底」とは、ごく平凡なものごとを徹底して行うことを意味する言葉。会社のスローガンや、著名人の座右の銘としてもよく使われているとのことです。
① 目的の不在、目的が見えにくい
もともと「丁寧な暮らし」は、自分や家族の心身を整えるための手段。しかしSNSなどで可視化されることで、その丁寧さ自体が目的化してしまった面があるのでは。
→ 例えば、「ていねいな暮らし」としてイメージされやすい「味噌や保存食を手作りすること」そのものが目的になり、それを通じて得たいはずの「安心」「楽しさ」よりも、 “手間をかけている自分”がフォーカスされやすくなる。例え本人が家族の健康や自分の趣味を楽しむことを目的にしているとしても、人には伝わりづらく、ていねいさのためのていねいさ、というふうに捉えられやすいのかもしれません。あくまで私的空間に限られた発想と捉えられがち。
一方、「凡事徹底」は、公的な社会活動の中で用いられる言葉で、明確な目的に向かって、ていねいにひとつひとつ積み上げていこうというように、対外的に目的が伝わりやすいので揶揄の対象になりにくいのではないでしょうか。
② 自己完結的で、社会との接点が薄い
「ていねいな暮らし」は自己充足的な世界で完結しやすいもの。
静かで内省的な価値観ではあるけれど、社会との関わりや他者との連帯が見えにくくなると、「閉じた世界」「現実逃避」と見なされがちです。
社会が不安定であるほど、「現実から距離を取る姿勢」に違和感や反発が生まれやすいこともあるのでは?例えば、値上げが続いてコスパやタイパが叫ばれる時代に、手間ひまかける「ていねいな暮らし」は、その逆をいく行為なので、甘い理想だと批判の対象になりやすい場合もあるかもしれません。
③ 優劣に繋がりやすい構図
“手間をかけられる余裕”が、いつの間にか優位性の表現になってしまうという側面もはらんでいる?
“ていねいに暮らせる=上質な人”という構図が浮かんで、本人の意図しないところで、それが無意識のマウンティングになることも。
掃除や整理整頓をしっかりやるという同じ行為でも、凡事徹底は統合への同調圧力として機能、ていねいな暮らしは差異化への誘導として機能してしまう。
そして差異化は優越性を示し、同時に劣等感も生み出す。
「ていねいな暮らし」が揶揄されるのは、そのていねいさが目的化し、閉じ、優劣を生むとき。

まとめると、凡事徹底という言葉の先には、明確な目的があり、その目的に向かうために他者とのていねいな関わりが必要であるという背景が含まれています。ていねいな暮らしの先には、その目的、他者や社会との繋がりのためという目的があったとしても見えにくい、伝わりづらい側面があります。
でも、実際に所謂「ていねいに暮らしているように見える人」は、自分を整えることで他者との関係も整えることを目的にしているのではないでしょうか。
例えば、誰かの話を急がずに最後まで聞くこと。
ありがとうを、きちんと目を見て伝えること。
そうした「関係のていねいさ」は、自己完結ではなく他者とつながるためのていねいさ。
そのためには自分の気持ちや生活を整えることが大切。人によって方法はそれぞれで、そのためにゆっくりコーヒーを楽しんだり家の整理収納に力を入れたりするのかもしれません。
話が堂々巡りになってしまいました。
わたし自身はていねいに暮らしている実感はなく、合理的にやりたいように生活を回しているのですが、以前から「ていねいな暮らしはなぜ批判の対象になるのか」という疑問があったので、この本を読んで少しすっきりしたところがあります。


