この本、納得感がすごくあったものの、一度読むだけではまだ自分の中に落とし込めていない感覚があって、なかなかブログに書けないでいました。
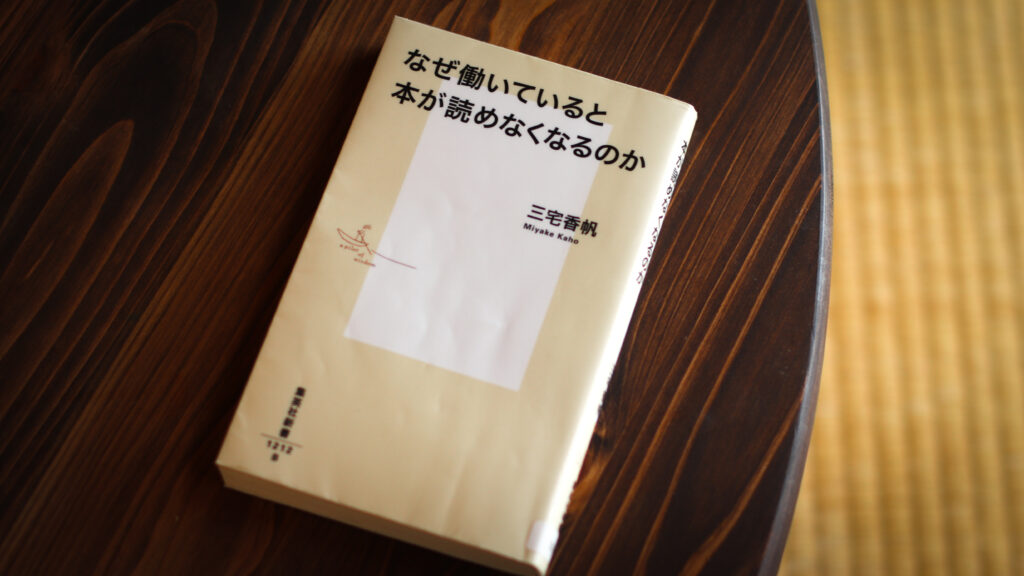
最近、著者である三宅香帆さんがこの本に関して言及されているYouTube動画を見たりしながら、やっと書くことができそう…ということで、わたしが理解した範囲でまとめてみようと思います。
【時代によって本の存在価値は変わってきた】
《1990年以前は政治の時代=内面の時代》
・社会参加あるいは自己探索の欲望
・社会のことを知ることで社会を変えることができる、自分を知ることで自分を変えることができる
《1990年代以降の経済の時代=行動の時代》
・社会のことを知っても自分には関係ない
・それより自分でコントロールできるものに注力したほうがいい
→インターネットの台頭ともに、自分にノイズのない情報を与えてくれることの価値が高まる。
『ノイズ』とは、「他者や歴史や社会の文脈」(つまり自分でコントロールできない=関係ないと思われがちな事象)
情報=知りたいこと
知識=ノイズ+知りたいこと
・ネットの世界は求めているもの(情報)だけを提示してくれる=自己啓発書と似ている。(自己啓発書は今の自分に必要なノウハウを端的に教えてくれる=ノイズを除去する姿勢が特徴)
・実際、読書離れと自己啓発書の伸びは反比例していて、自己啓発書の売れ行きは伸びている。
・自己啓発書以外の文芸書などはノイズ。知らなかったことを知ることがノイズ。
・働いて疲れていてもゲーム、スマホならできるのは、コントローラブルな娯楽だから。知らないノイズが入ってこない。これを快適に感じている。
・コスパやタイパが叫ばれる時代だから、ノイズを消去してすぐ答えに辿り着きたい、すぐ自分の求めていることに辿り着きたいという頭になっている。
・読書は何が向こうからやってくるかわからない。知らないものを取り入れるアンコントローラブルな娯楽。
→このノイズ性が人が読書を手放す原因なのでは。
実際にこの本(「なぜ働いていると本が読めなくなるのか」)も、いきなり主題の答えを提示するのではなく、まずはこれまでの時代において本がどのような位置付けをされていたかという経緯や、「花束みたいな恋をした」という映画から引用しての解釈が多用されている。
本書の最後の方にやっと、では現代人が本を読むためにはどうすればいいのかに言及されといる。でもここまでの前段階の文脈を把握しているからこそ、最後の解の部分に対しての理解が深まるという事象が起こっているのだと、読みながら実感しました。
・読書で得られる知識にはノイズがある。小説には予想していなかった展開や知識が登場。
読者が予期しなかった偶然出会う情報を知識と呼ぶ。
・情報はノイズが除去された知識=ライフハック。
・読書とは自分から離れた文脈に触れること。
本が読めない状況とは新しい文脈をつくる余裕がない、新しい文脈をノイズだと思ってしまう
自分に関係のあるものばかり求めてしまう
余裕のなさゆえ。
少し話はそれますが、レシピ本を読書本と位置付けたとしての話。
鶏肉と大根あるから、手軽においしくできるレシピを探したいとなったとき、やはりまずスマホで検索しがち。ピンポイントで鶏肉と大根に特化したレシピを挙げてくれる。
一方でレシピ本を開いた場合。鶏肉レシピを探しつつも目には豚肉や大根以外の野菜を使ったレシピが入ってくる。そうすると「やっぱりこっちに変えようかな」などとなって頭の中はぐるぐる考える。
このノイズ性を楽しめない(=時間と心に余裕のない)現代人は、やはりノイズが除去されたネットの世界に頼る。

わたしが読み解いた「本を読めない理由」は2つ。
ひとつは、ノイズを除去したいという思考に至る現代人の働き方や、働き方からくるコスタイパ重視のライフスタイル。
もうひとつは、自己と社会の分断が進んでいること。
昔は本を読んで教養を高めて社会を変えたい、社会は変わるものだった。社会=自己の構図。
今は教養を高めたところで何も社会は変わらない。それなら自分の力でコントロールできる自己を磨こう。自己啓発書やノイズのないコスパタイパへ移行。いかに効率よく自己を高められるかにフォーカス。社会≠自己の構図。
最近読んだ別の本「去られるためにそこにいる」にもこんな記述がありました。
「教育のシステムが時代に合わなくなってきたことで、不登校が増えた。根性なしの子どもや不真面目な子どもが増えたため、ではない。それと同じように「どう生きるべきか」とか「幸福とは何か」ということの意味が変化してきて…」
「「人はなぜ働くと思うか?」という質問に、高校生たちはお金のため、名誉のため、楽しみのためなどと答える。昔なら当たり前に出たはずの「社会のため」という答えが最後まで出てこなかった。」
働くのは生活のため、お金のため=自己。
ここでも社会と自己の分断がみられるのではないかと感じました。
夫とこの話をしていて、今は社会において「無いモノが無い」から社会と自己の分離が起こっているのでは?となりました。
まだ何も揃っていなかった頃は、新しい技術を開発すること、その会社の労働力になることが社会に繋がっていた。
あらゆる便利なシステムや機械は開発され尽くした今、もはや付加価値をどこに置くかレベルの企業間の争い。そこに社会との繋がりや達成感は見出せず、ベクトルは自己へ向いていく。
便利な世の中の副作用なのか、より自己を高めることに集中でにる良い時代になったと解釈するのか。

長くなりましたが、「なぜ働いていると本が読めなくなるのか」という主題テーマからさらに広がって、様々なことを考えさせられたり気付かせてもらえる一冊でした。


