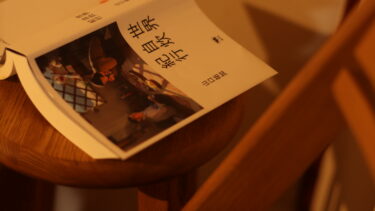いよいよ12月を目前に控え、一年の終わりを感じることが増えてきました。
とはいえ、よく考えると、自分自身の日常生活から一年の終わりを感じているのではなく、周りの環境(ラジオやSNSなど)を通して「もうすぐ今年も終わるね」「今年やり残したことは」「来年はこんな一年にしたい」という言葉を耳にすることで、自然と自分もその流れに乗って一年の終わりを感じているような感覚。

年末、と聞くとどうしても“締めくくり”のイメージが強くあります。
でも、人それぞれの生活のリズムを見てみると、実は年末が必ずしも区切りになっていないことって多いのではないでしょうか。
たとえば、仕事が年度単位で動いていて3月が区切りになる場合。会社員時代のわたしがまさにそうでした。人事異動も含めてガラッと環境が変わるのは3月と4月の変わり目。
子どもの進級や進学も同じく春のタイミング。
だから、年末に無理して全部を片付けようとすると、意外に合理的でないこともあるような気がしています。
仕事関係の書類や、子どもの学用品・作品の整理も、区切り(締め)が来る年度末に行うほうがスムーズかもしれません。
年末はあれこれ全部に片をつけるのではなく、「気持ちよく年を越せるかどうか」を基準に、すること・しないことを分けていくことが必要ではないかと考えています。
■ 年末は“途中経過”
まず大前提として、
年末=絶対に締めないといけない区切り
ではなくて、
年末=長い流れの一部、途中経過
だと捉えてみる。
この視点が入るだけで、「これは今やらなくてもいいかも」と思えることが一気に増え、社会の流れ的に自然と気忙しくなってしまう自分の気持ちを少しクールダウンすることができます。
年度区切りで進んでいる仕事や学校関連の整理みたいに、年末と関係ないサイクルのものは、無理に片付けなくてOK。
そのかわり、“気持ちよさ”だけを基準に、小さく区切りをつけてみる。

■ 「これだけは持ち越したくない」だけ締める
では何を整理するか。
それは、
“来年に持ち越すとずっと気になってしまうもの”だけ。
例えば、
・メールで返せていない返信がひとつだけある
・心のどこかにずっと引っかかっている仕事がある
・年内に確認しておきたい書類が一枚ある
わたしが会社員の頃は、この案件を残しておくと、せっかくの長期連休中にもモヤモヤしてしまう〜というものだけ仕事納めの日までになんとか終わらせていた記憶があります。
そういうものをピックアップして優先度を上げてみる、というやり方もひとつかなと思います。
こういう「静かなストレスの種」だけ、小さく区切りをつけておくと、年の越え方がまったく変わるような。
逆に、
・気にならない作業
・年度や別サイクルで動いているもの
・やってもやらなくても変わらない家事
これらは、あえて “しない” と決めてみる。
年末は、全部終わらせる区切りではなくて、気持ちよく越えるために、要点だけ整えるタイミングとして有効活用できたらなと。

■ 「気持ちよく越える」という基準は、人によって違う
そしてもうひとつ大事なのは、気持ちよく越えるための基準は、ひとりひとり違うということ。
年末や年度末という区切り以外にも、仕事の決算月だったり、家族の記念日だったり、「気持ちの切り替わり」が自然に訪れるタイミングはそれぞれ。
たとえば、
• 会社員なら決算月が“節目”
• 自営業なら繁忙期の終わりが“締め”
• 農業や季節の仕事なら、自然サイクルで一年が動く
そして締めのタイミングはその都度変わるもの。
わたしは会社員の頃は年度末が締めだったのですが、在宅フリーランスになってからは、どちらかというと年末が締め。確定申告に向けて必要な準備をしながら、今年一年の仕事を振り返るタイミングでもある。このように、自分や家族の生活スタイルの変化によって、締めのタイミングは変わってきます。
話が少し逸れましたが、年末をすべての締めと捉える必要はないということ。
大切なのは、世の中の“年末っぽさ”に合わせることではなく、自分自身のリズムで区切ること。
もし迷ったら、「これを持ち越したら、来年の私が困る?」と問いかけてみる。
もし困らないなら、今はやらなくていい。
困るなら、小さく手をつけておく。小さく整えておく。
この線引きを意識しながら、気持ちよく年末に向かっていけたらと考えています。
ちなみに、12月特有の空気はわたしは好きです。街ゆく人が少し足早になっていたり、クリスマスやお正月の飾り、スーパーにはイベントのご馳走が並んでいたり。そんな年末感漂う空気は楽しく味わいたい。でも必要以上に気忙しくならないように。ここの塩梅は難しいですが、最近はこんな風に考えています。