ラジオ「ジェーン・スー 生活は踊る」のお悩み解消コーナーに先日寄せられていた相談が「4歳の子どもにどこまで親がレールを敷くべきか」という内容でした。
この“親がレールを敷く問題”、わたしも所々で立ち止まって考えることがあります。
2年前のブログに書いているのが、キンコン西野さんがVoicyで話されていた「俺はガードレールになるだけ」という言葉から、子育てにもこの考え方を軸にしていきたいということ。
親としてはレールを敷くのではなく、ガードレールのイメージでありたい。基本的には子どもの思うがままに自由に動き回ってもらって、明らかに道を踏み外しそうになった時だけガードする役割。
つい先に手出し口出しをしてしまう自分には、このぐらいの感覚でいる子どもとの距離感がちょうど良いのかもしれません。
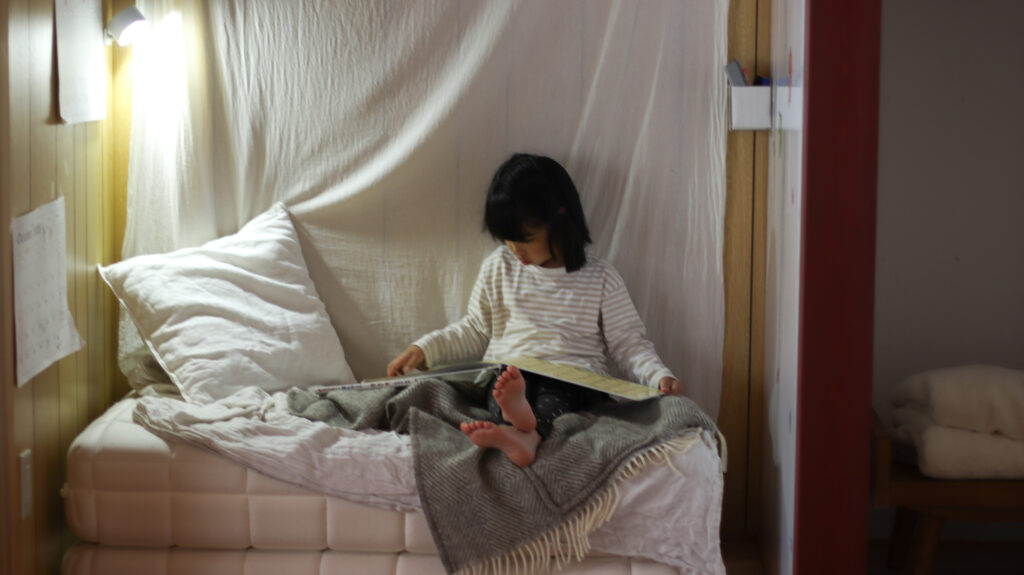
ただ、これまで何度も考えてきたことをラジオで改めて相談されている話を聞いて、ガードレールよりもさらにしっくりくるイメージがふと浮かびました。
それは、三角コーンです。
工事現場やイベント会場などで立ち入り禁止エリアに置いてある、あれです。
ここからはわたしの感覚的な話になるのですが、ガードレールをイメージした場合、いつの間にかガードレールの幅を狭めてしまって、気付けばレールを敷いているということになりかねないな、と。
親としては限界ギリギリのラインにガードを敷いていたとしても、気付かぬうちに子どもにこうあってほしいという要望が強まり徐々に右と左のガードレールが真ん中に近づき、一本のラインになってしまう=レールを敷くという状況になりかねない。
一方で、三角コーンの場合。
広い芝生のイベント会場があったとして、子どもはそこを自由に走り回っている。親としては危ない池や水路といった部分的な場所にだけコーンとバーを置く。
わたしは会社員の頃、イベントを開催することの多い部署にいたのでよくわかるのですが、コーンって持ち運びにくい形状かつ意外と重たい。なので、ちょっとやそっとのことで気軽にひょいと位置を変えようとしない→子どもを特定のレールに行かせようと立ち入り禁止エリアを安易に拡大しようとはしない。

気持ち的にはわたしはコーンとバーを常に保持しながら子どもを見守っていて、そろそろ本気で道を逸れそうだなと思った時にやっと動き出すぐらいの感覚です。
タイトルとしては「レールを敷く」と「ガードレールになる」が対比として分かりやすいのでこうしましたが、最近はガードレールよりもさらに部分的な「コーンを置く」イメージの親でありたいなと感じています。


