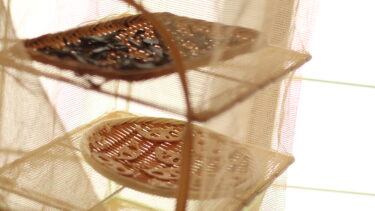前回の続き。
片耳にイヤホンを付ける習慣を見直したくて、家族がいるときはイヤホンを外す生活を続けてしばらく経ち気付いたこと。
家事をするとき、子どもと一日中一緒に過ごすとき、わたしは片耳イヤホンをしていないと「できない」と思い込んでいたんだなぁということです。

思い返せば、ラジオを聴きながら家事を始めたのは3年ほど前。当時、苦手な家事や言葉が通じない子どもを相手と向き合う日々は、どこか別のところに少し意識を飛ばしておくほうがイライラせずに済むと気が付いて以来の習慣。片耳にイヤホンを付けてラジオを聴くようになりました。
子どもたちが幼かったので特に大人と会話したいという欲が強かったこと、手を動かしながら情報を得たいという欲があったように思います。
たしかにその頃は効果テキメンだったような。イヤイヤ全盛期の年子姉妹の相手をするには、100%子どもに集中するよりも、イヤホンしてる方が程よくイライラしすぎなかった気がします。
元々は家事のモチベーションが上がらないからイヤホンをする、子どもの声をずっと聞いているのがしんどいからイヤホンをする、という緊急避難的存在だった片耳イヤホン習慣。
いつしか「家事をする=イヤホン、子どもといる時間=イヤホン」というように、モチベーション如何に関わらず、「その状況になれば最初からイヤホンをする」というように、自分の中でルーティンを書き換えてしまっていたのです。
数年前は家事全般が嫌で嫌でしょうがなかったのですが、今は洗い物や洗濯物干しはあまり苦もなくできるようになっています。(相変わらずトイレ掃除が嫌いなため、この時間だけはイヤホンしていることは前回記事のとおり)
子どもたちも成長とともに会話ができるようになり、「言葉が通じない相手」ではなくなっているのに、わたしのルーティンが変わっていないままだった。子どもの変化に対して、わたしのルーティンがアップデートされていなかったということ。

何でもルーティン化するのが好きなわたし。
選択肢を極力減らすことで迷う時間をなくし、効率的合理的に動くには一番の方法。
ただ、今のルーティンは家族の動きや自分の働き方との関係性のうえで成り立っているもの。

その時々で見直しが必要だということを、イヤホンタイムを見直すことで改めて痛感しています。