子どもの前で本を開くのは平気なのに、スマホを見るのに罪悪感を覚えるのはなぜなのか。
スマホで本を読んでるかもしれないのに。
子どもと一緒にスマホでYouTube観たり音楽聴くのは良いのに、イヤホンで聴くことに罪悪感を覚えるのはなぜなのか。
耳から学びを得ているかもしれないのに。

この罪悪感の正体、わたしは2つあると考えています。
①将来の子どもに真似してほしい姿ではない
スマホ → 「子どもに真似してほしくない姿」だから罪悪感を抱く
本 → 「子どもに真似してほしい姿」だから罪悪感を抱かない
つまり、「いま自分がしている行為を、子どもに見せてもいいと思えるかどうか」が罪悪感の分かれ目なのかもしれません。
スマホやイヤホンは閉鎖的なので、子どもが何をしているかわからない不安感から、親としてはあまり真似してほしくないという気持ちになっているのだと思います。
②親の姿として将来子どもに覚えていてほしい姿ではない
わたしが母の姿として一番よく覚えているのは、台所に立っているところ。冬は割烹着を着て壁付けキッチンで作業している後ろ姿。
わたし自身は、取り立てて台所にいる姿を娘たちに覚えていてほしいというわけではありません。
よく畳の上に寝っ転がって昼寝してたなとか、そんなレベルでも良いのです。
ただ、スマホを片手に持っている姿が一番目に焼きついている…みたいな状況は切実に避けたい。
これも子どもの前でのスマホを触る時の罪悪感のひとつの要因なのではないでしょうか。

そして①②に共通して言えることが、この罪悪感はデジタル画面の大きさに反比例するということです。
スマホよりも大きなデジタル画面、例えばタブレットやパソコンがわが家にはあります。
スマホ→タブレット→パソコンの順に画面は大きくなるけれど、その順番で罪悪感は薄くなる。まさに反比例しています。
タブレットやパソコンはスマホほど罪悪感を感じない(わたしの場合)理由、最も大きな要因は、やはり閉鎖性にあると思います。
パソコンやタブレットは複数人で覗き込むことができるので、割とオープンなデジタル機器。子どもが見ているものを親も把握できるという点で、スマホほど閉鎖性がなく安心感があるからなのでは。
本も一人で読むという点での閉鎖性はありますが、何の本を読んでいるのかなどは周りにも分かるので、閉鎖性という観点からしてもスマホとはやはり性質が異なります。
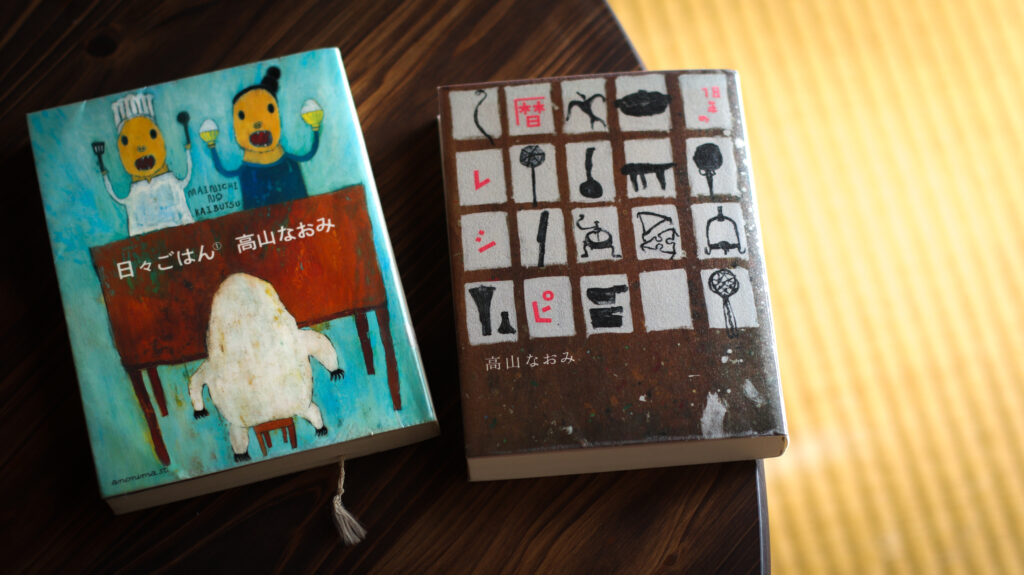
ここでもう一つ気づいたこと。
それは、わたしのスマホに対する固定観念が強いということです。
スマホを触る=「自分の快楽や惰性のために時間を使っているように見える」
本を読む=「学びや豊かさを得ているように見える」
というイメージの違いが固定化されすぎている。
スマホと本の中間に位置していそうなパソコンは仕事をするためのツールという認識ゆえに罪悪感がないという、ここでも自分の固定観念の強さを感じます。
実際には、スマホだって情報収集や学びに使う場合もあるし、本だってただの娯楽読みもある。
夫のスマホにも固定観念が発生していることがしばしば。
朝から家族四人で遠出をする日、わたしは家事や子どもの準備でひとりバタバタ動き回る中、夫はずっとスマホを見ている。この状況、モヤモヤしませんか?
でも夫は夫で、目的地の駐車場情報や道路の混雑具合など、どのルートで行けばスムーズかスマホで調べてくれているのです。
そう考えると、出掛ける準備としては分担できている。むしろわたしにの苦手分野を調べてくれてありがとうという感謝の気持ちすら生まれてくるのです。
なのに、スマホを触っているというだけでなぜか「遊んでいる」と決めつけてしまう偏見。

子どもの前でスマホを触る時間を減らしたいと思うのと同時に、そもそもスマホへの偏見を是正していかないと、これからますますスマホを生活に取り入れる(学習面でも友達付き合いでも)娘たちへの許容範囲を狭めてしまうことになりそう。
スマホ育児をしすぎるのも問題だけど、スマホ=悪だと決めつけすぎる親も子にとっては害。共同生活しにくくなって、かえって子どもは親の目を盗んでスマホを触るようになる。一番避けたい「閉鎖性」をより促進してしまう結果になりかねません。
何より子育てにおけるスマホの弊害は、使うことではなく、その閉鎖性によるものだから。
矛盾しているかもしれませんが、子どもの未来に残したい姿かどうかを考えると、わたし自身は少しスマホと距離を置きたい。でも、子どもとのこれからの生活を考えると「スマホ=娯楽、悪」だという認識も改めないといけません。
答えのない長い問題になりそうですが、結論は出なくても、こうしてスマホやデジタル機器について考える時間を持つこと自体は有意義だと(信じて)考えています。


